切削工具は工作機械に取り付けて使用する刃物の総称ですが、中でも特定の目的に合わせて設計された機器を特殊切削工具といいます。今回は、特殊切削工具の概要について詳しく解説していきます。選び方のポイントもまとめているので、ぜひ最後までご覧ください。
もくじ
特殊切削工具とは

特殊切削工具とは、一般的な既製品では対応できない加工や、特定の目的に合わせて設計・製作される切削工具を指します。市販のドリルやエンドミルでは困難な加工に対応するため、形状や材質、刃先の仕様などをカスタマイズして作られることが一般的です。
主に高い精度が求められる部品の製造現場や、加工効率を最大化する必要がある生産ラインで使用され、加工時間の短縮や製品の品質向上に大きく貢献します。工具の長寿命化にも一役買ってくれるため、交換頻度を減らせるというメリットも。
生産コストの削減にも繋がる特殊切削工具は、製造業において重要な存在だと言えるでしょう。
特殊切削工具が使われる産業
特殊切削工具は、以下のような様々な産業で活用されています。
- 自動車
- 航空宇宙
- エネルギー
- 医療
- 電子機器製造
こうした産業では製品の性能や安全性に直結する高い加工精度が要求されるため、特殊切削工具の存在は欠かせません。
例えば、自動車産業ではエンジン部品やトランスミッション、ブレーキ部品など、複雑かつ耐久性が求められる部品を効率的に加工するために使われます。
医療機器の分野では、極小部品やステンレス製のパーツなど、精密かつ衛生的な加工が必要であり、細かな用途に応じた専用工具が使用されることが一般的です。
特殊切削工具を用いる加工

特殊切削工具は穴あけや平面切削など、様々な加工に用いられます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
穴あけ
穴あけ加工は、機械部品や構造材に正確な位置と深さの穴を開けるための基本的な工程です。しかし、次のような場合には、専用設計された特殊ドリルが必要になります。
- 斜め面や湾曲面への穴あけ
- 高硬度材への加工
- 下穴なしでバリを抑えた穴加工 など
こうした加工に用いる特殊切削工具は、刃先の仕様や工具形状、コーティング材質を細かく調整することで、穴の精度や加工スピードの向上、工具寿命の最適化に貢献してくれます。
複数の穴開け工具を段付き形状にすることで工程を集約し、生産性の向上に繋げるケースも多いです。
平面切削
平面切削はフライス加工の1つで、材料の表面を平坦に仕上げるために行います。工作物の精度や寸法管理に直結する重要な工程です。
一般的にはフライスカッターやエンドミルが用いられますが、切削面の材質や形状、要求される精度によっては、既製の工具では不十分なケースも少なくありません。
例えば、アルミ合金やチタン合金といった異種材料を同時に切削する場合や、製品上面に厳しい幾何公差が求められる場合には、特殊な刃先設計を持つ切削工具が必要となります。
ねじ切り
ねじ切り加工では、ボルトやナットといった締結部品を製造するために、精密な螺旋状の溝(ねじ山)を形成します。寸法精度を確保するため、専用の工具が用いられることが多いです。
高い精度が求められるためコストも大きくなりますが、自動車や航空機など、安全性が求められる産業には欠かせません。切削加工で作られたねじは、用途に応じて防錆塗装やメッキ処理を施すことで、耐久性が高まります。
特殊切削工具の材質
特殊切削工具には、用途によって異なる材質が用いられます。以下、それぞれの特徴を解説します。
超硬合金
超硬合金(ちょうこうごうきん)は、タングステンカーバイド(WC)にコバルトなどの金属を結合材にして焼結した硬質材料。特殊切削工具でよく使用される素材の1つです。
特徴としては、高い硬度と耐摩耗性があり、高速回転など負荷がかかる切削環境でも形状の保持性が優れている点が挙げられます。
ただし、靭性が低く、刃先の欠けが起こりやすいのはデメリットだと言えるでしょう。衝撃に弱く、落下や断続的な加工によって破損するケースも少なくありません。
PCD
PCD(多結晶ダイヤモンド)は、ダイヤモンドの微結晶を金属やセラミックスの粉と一緒に高温・高圧で焼結した人工鉱物のことです。あらゆる方向からの力に強く、割れたり剥がれたりしにくいという性質を有しています。
極めて高い硬度を持ち、硬度や熱伝導性に優れているのが特徴。高速切削が可能である点や、摩耗しにくく工具寿命が長い点が強みです。
一方で、高温下では鉄に反応して摩耗してしまいやすく、鉄系鋼材の加工や切削にはあまり向いていません。主に非鉄金属(アルミニウム合金、銅合金)、非金属材料の切削に多く使用されます。
セラミック
セラミックは、非金属でありながら高い硬度と耐熱性を持つ素材として、特殊切削工具にも用いられています。酸化アルミニウム(Al₂O₃)や窒化ケイ素(Si₃N₄)を基にした工業用セラミックは、高速加工において安定した性能を発揮します。
高速回転でも刃先が摩耗しにくいほか、熱伝導率が低いため温度上昇による硬度低下も起こりにくいのが特徴です。一方で、靭性が低く衝撃や振動に弱いため、切込み量、送り速度の管理が重要になります。
鋼材
鋼材は特殊切削工具の中でも古くから使用されてきた素材で、高速度工具鋼(ハイス鋼)が代表的です。ハイスはタングステン、モリブデン、クロム、バナジウムなどを含む合金鋼で適度な硬度と靭性を兼ね備えており、汎用性の高い切削工具素材として知られています。
超硬合金などに比べると硬度、耐摩耗性は劣りますが、衝撃に強く複雑な形状や微細な刃付けがしやすいため、特殊な形状においても優れた加工性を発揮します。再研磨が可能で、コストパフォーマンスに優れる点もメリットの1つです。
特殊切削工具を選択するポイント
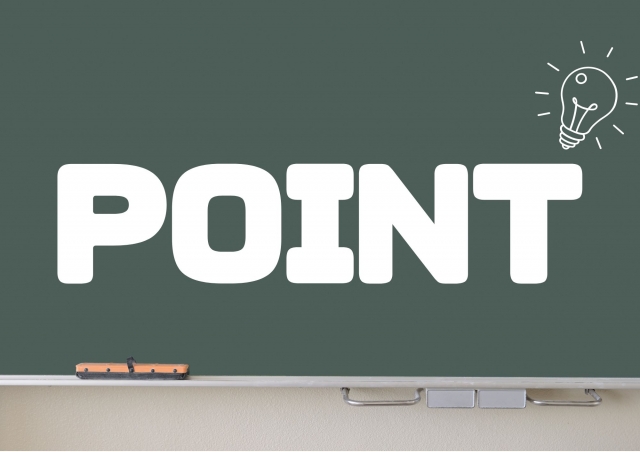
特殊切削工具を選定する際は、用途、材質、形状などを確認することが大切です。
材質
特殊切削工具は、用途に応じて、以下のようにさまざまな材質で作ることが可能です。
| 材質 | 特徴 | 用途 |
|---|---|---|
| 超硬合金 | 高硬度・耐摩耗性・高温に強い | 一般的な金属加工、高速切削 |
| ハイス | 靭性に優れる・加工性が高い | 低速加工、小ロット品、複雑形状 |
| ダイヤモンド | 最も硬いが鉄には不向き | アルミ、銅、樹脂、カーボンなど非鉄材料 |
分類
特殊切削工具には様々な分類があり、刃先の仕様や刃数、溝形状などのカスタマイズが可能です。各工具に適した加工は以下の通りです。
- ドリル:穴あけ加工、下穴加工
- エンドミル:溝加工、ポケット加工
- バイト:旋盤による外径・内径加工
加工対象の材質や分類、必要とされる精度に応じて最適な形状を選ぶことが、安定した生産とコスト削減のポイントになります。
コーティング
切削工具のコーティングは工具の寿命を延ばし、加工精度や能率を向上させるために欠かせない技術だと言えます。
代表的なものとしては、以下が挙げられます。
- TiN
- TiALN
- TiCN
- DLC
例えば、TiN(窒化チタン)は汎用性が高く、幅広い材料に対応できる基本的なコーティングです。非鉄金属や樹脂加工では、摩擦や溶着を抑えるDLC(ダイヤモンドライクカーボンやダイヤモンドコートが適しています。
特殊切削工具選びは専門家への相談が不可欠
特殊切削工具の選定は専門的であり、次のような要素を総合的に判断する必要があります。
- 材料の特性
- 加工条件
- 生産量
- 設備環境 など
そのため、検討の段階で専門家に相談することがスピーディーな導入に繋がるでしょう。
メーカーや工具商社では、現場の課題やニーズに最適な工具の提案、素材、加工条件に合わせた工具設計などを行ってくれます。切削試験やサンプル提供で実際の使用環境での検証を行えるケースもあり、効率的な工具の選定が可能です。
特殊切削工具の入手方法
特殊切削工具は使用目的や加工対象に応じて設計・製作されるため、一般的な通販サイトやホームセンターなどでは入手が困難です。主な入手ルートとしては、専門の工具メーカーや切削工具を取り扱う商社、販売代理店などが挙げられます。
フルオーダーだけでなくセミオーダー形式を採用している企業もあり、コストや納期のバランスを考慮した柔軟な選択が可能です。工具の再研磨やコーティングといったメンテナンスを含めたサポート体制も、メーカー選びの重要なポイントになります。
特殊切削工具は用途に合わせて選ぶ
特殊切削工具は様々な産業の部品や製造に欠かせないものです。しかし、用途や削材に適したものを選ばないと破損などを招き、生産性に悪影響を及ぼしかねません。
特殊切削工具を導入する際は、材質の特性や精度についてしっかりと理解し、専門家のアドバイスを受けた上で選ぶことが大切です。
おすすめの特殊切削工具メーカー
-
短納期 なら!
-
技術力 なら!
-
高品質 なら!

あらゆるニーズに応える豊富な商品ラインアップを取り揃え、最適なソリューションを提供します。ラインナップにない特殊な工具でも、即時設計して幅広いニーズに対応可能です。
-
提案力 なら!
この記事の執筆者
特殊切削工具メーカー比較サイト編集部
おすすめの特殊切削工具メーカーを厳選してまとめた比較サイトです。特殊切削工具に関する基礎知識からメーカーを選ぶ際のポイントなども紹介しています。一般切削工具では対応が難しい形状の加工や生産効率アップの実現のため、特殊切削工具の導入を必要とする製造現場の担当者様に役立つ情報をまとめましたので、ぜひチェックしてください。



